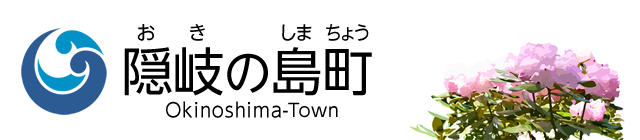国民健康保険で受けられる給付について
病気やけがをして医療機関にかかったとき、また出産や死亡があったとき、総医療費の一部を支払うだけで診療を受けることができ、また次のような給付を受けることができます。
給付を受けられる場合は、役場本庁及び各支所・出張所で申請してください。
※交通事故等で保険証を使って受診する場合はこちらをご覧ください。
- 療養の給付(自己負担割合)
- 療養費
1.急病のためマイナンバーカード又は、資格確認書(保険証)なしで受診したとき
2.医師が必要と認めたコルセット等治療用装具を作ったとき
3.医師が必要と認めた小児弱視等治療用眼鏡及びコンタクトを購入したとき
4.医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき
5.海外渡航中に病気やけがで現地の医療機関を受診したとき
6.移送費
- 高額療養費
国民健康保険で受けられない給付
次のような場合は国保での診療は受けられません。
≪病気とみなされないもの≫
・正常な妊娠・出産
・美容整形
・歯列矯正
・健康診断、ドック
※健康診断、ドックについてはこちらをご覧ください
・予防注射(ただし、破傷風、狂犬病、はしか、百日ぜきは感染のおそれがある場合のみ認められます)
≪業務上のけがや病気≫
・労災保険が適用されるか、労働基準法にしたがって雇い主の負担となります
≪その他≫
・けんか、酔っぱらいなどが原因のけがや病気
・わざとした行動や犯罪を犯してのけがや病気
・医師や保険者の指示に従わなかったとき
療養の給付(自己負担割合)について
病気やけがで診療を受けるときは、保険証を医療機関へ提示して、かかった医療費の一部(一部負担金)を医療機関の窓口で負担します。年齢などによって一部負担金(自己負担金)の負担割合が異なります。負担割合は次のようになります。
医療費の一部負担金(自己負担金)の割合
| 区分 | 一部負担金(自己負担金)の割合 |
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満(一般・低所得者1・2) | 2割 |
| 70歳以上75歳未満(現役並み所得者) | 3割 |
70歳以上75歳未満の人の所得区分
70歳になると、所得区分に応じて自己負担割合や自己負担限度額が変わります。保険証の右側に負担割合が記載されていますのでご確認ください。
所得区分
≪現役並み所得者≫
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下記(1)(2)(3)いずれかの場合は申請により「一般」の区分と同様となります。
| 同じ世帯の70歳以上75歳 未満の国保加入者数 |
収入 | |
| (1) | 1人 | 383万円未満 |
| (2) | 後期高齢者医療制度への移行で国保を ぬけた人を含めて合計520万円未満 |
|
| (3) | 2人以上 | 合計520万円未満 |
≪一般≫
同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる住民税課税世帯の人。また住民税課税所得が145万円以上
でも、70歳以上75歳未満の国保加入者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の人。
≪低所得者2≫
同じ世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)。
≪低所得者1≫
同じ世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得
がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。
療養費について
次のような場合は、とりあえず自分で全額を支払い、必要書類を添えて申請すると、保険で認められた部分について、支払った額の7割(又は8割)を国保から払い戻してもらうことができます。
ただし、療養費の申請には時効(2年)があるため、該当の場合は速やかに手続きをしてください。
※世帯主が申請者になります。申請者が世帯主以外の場合、委任状(20KB)(Word文書)が必要になります。
| 申請内容 | 必要なもの |
| ・急病などでやむを得ず保険証を提示せずに治療を 受けたとき |
・診療報酬明細書の写し(レセプト) ・領収書 ・マイナンバーカード又は、資格確認書 ・振込口座のわかるもの(通帳など) ・受診者及び世帯主の個人番号が確認てきるもの(マイナンバーカードなど) ・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マインバーカードなど) |
| ・医師が必要と認めたコルセットなど治療用装具を 購入したとき |
・医師の証明書(意見書) ・領収書 ・マイナンバーカード又は、資格確認書 ・振込口座のわかるもの(通帳など) ・受診者及び世帯主の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど) ・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
| ・医師が必要と認めた9歳未満の小児弱視等治療用眼 鏡及びコンタクトを購入したとき |
・医師の指示書等(検査結果が含まれているもの) ・領収書 ・マイナンバーカード又は、資格確認書 ・振込口座のわかるもの(通帳など) ・受診者及び世帯主の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど) ・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
|
・医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき |
・医師の輸血証明書 ・生血代金領収書 ・マイナンバーカード又は、資格確認書 ・振込口座のわかるもの(通帳など) ・受診者及び世帯主の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど) ・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
| ・海外で病気やけがにより医療機関で治療を受けた とき (治療目的に渡航した場合を除く) |
・診療内容の明細書と領収明細書(和訳が必要) ・領収書 ・印鑑 ・マイナンバーカード又は、資格確認書 ・パスポート ・振込口座のわかるもの(通帳など) ・受診者及び世帯主の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど) ・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
| ・緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に 要した費用を負担したとき ・移植にかかる臓器の輸送に要した費用を負担した とき |
・医師の同意書 ・移送費の明細及び領収書 ・マイナンバーカード又は、資格確認書 ・振込口座のわかるもの(通帳など) ・受診者及び世帯主の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど) ・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
高額療養費について
同じ月(1日から末日まで)にかかった医療費の一部負担金の額が一定の金額を超えた場合、その超えた金額を高額療養費として支給します。(食事代、病衣代、個室代などの自費部分は対象外)
・高額療養費に該当する世帯には、診療月の約3か月後に申請手続きの案内をしています。なお、診療日の翌月1日から2年(自己負担分を診療月
の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日から数えて2年)を過ぎると時効となり、支給できません。
【申請に必要なもの】
・高額療養費支給申請書
・振込口座のわかるもの(通帳など)
・受診者及び世帯主の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
※世帯主が申請者になります。申請者が世帯主以外の場合、委任状(20KB)(Word文書)が必要になります。
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※令和4年10月診療分から高額療養費の支給申請手続きが簡素化されました。
支給申請手続きの簡素化についてはこちらをご覧ください。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 所得※1 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降※2 | 限度額証 の申請 |
| 901万円を超える | ア | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 必要 |
| 600万円を超え 901万円以下 |
イ | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | 必要 |
|
210万円を超え |
ウ | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 必要 |
| 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 | 必要 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 | 必要 |
※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は区分アとみなされますので、収入がない場合でも申告する必要
があります。
※2 過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 保険証 負担割合 |
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※1 | 限度額証 の申請 |
||
| 外来 (個人単位) |
外来と入院 (世帯単位) |
外来 (個人単位) |
外来と入院 (世帯単位) |
|||
| 3割 |
現役並み所得者3 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 不要 | ||
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | 必要 | |||
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 必要 | |||
| 2割 | 一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円※2 | 57,600円 | 18,000円※2 | 44,400円 | 不要 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 8,000円 | 24,600円 | 必要 | |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 8,000円 | 15,000円 | 必要 | |
※1 過去12か月間以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間(8月~翌7月)の限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)は144,000円です。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請
医療費を支払うとき、窓口での負担を自己負担限度額までにするには、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
※70歳以上75歳未満の人で「現役並み所得者3」と「一般」の人は保険証の提示のみで限度額までしか請求されませんので「限度額適用認定
証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の作成は不要です。
【申請に必要なもの】
・マイナンバーカード又は、資格確認書
※来庁者が同一世帯以外の人の場合、委任状(20KB)(Word文書)が必要になります
マイナ保険証を利用すれば、上記の手続きなく、窓口での負担が自己負担限度額までになります。
役場での申請が不要になりますので、マイナ保険証をご活用ください。
高額療養・高額介護合算療養費について
同一世帯内で、国民健康保険と介護保険の両方を利用して、1年間に負担した医療費と介護費を合算し、自己負担額の合計額が限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
該当すると思われる世帯には、毎年2月頃申請書をお送りしますので、申請してください。
【注意】
・支給対象の計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
・自己負担額の合算は、加入する医療保険ごとに計算されます。同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できま
せん。
・自己負担限度額を超える負担が500円以上あった場合に支給します。
・70歳未満の人は一定の基準を超えたものだけが計算の対象となります。
(一定の基準:1か月の診療を個人ごと、医療機関ごと等に分け、21,000円を超えた場合)
・自己負担額には、入院時の食事代や差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。また国民健康保険の高額療養費、介護保険の高額介
護(予防)サービス費が支給される場合は、その額を差し引いた額となります。
70歳未満の人の自己負担限度額
| 区分 | 基礎控除後総所得金額※1 | 医療費+介護費の 自己負担限度額 |
| 上位所得者 | 901万円超~ | 212万円 |
| 600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
| 一般 | 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
| ~210万円以下 | 60万円 | |
| 住民税非課税世帯※2 | 34万円 |
※1 基礎控除後総所得金額とは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計になります。
※2 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人になります。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
| 区分 | 所得区分 | 医療費+介護費の 自己負担限度額 |
| 現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
| 現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
|
一般 |
課税所得145万円未満※1 |
56万円 |
| 低所得者2 | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
| 低所得者1 | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円※2 |
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 対象世帯に70歳未満と70歳以上75歳未満の人が混在する場合、まず70歳以上75歳未満の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担
額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。
入院したときの食事代等について
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。療養病床に入院する65歳以上の高齢者の人は、食費(食材料費・調理費相当)及び居住費(光熱水費相当)を自己負担します。
食事代等の減額を受けるためには事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
入院したときの食事代等の標準負担額 (70歳未満)
| 所得区分 | 食事代(1食あたり) | |
| 一般の人(下記以外の人) |
510円 |
|
|
住民税非課税世帯 |
過去12か月で90日までの入院 | 240円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 190円 | |
入院したときの食事代等の標準負担額 (70歳以上75歳未満)
| 所得区分 | 食事代(1食あたり) | |
| 一般の人(下記以外の人) |
510円 |
|
|
低所得者2 |
過去12か月で90日までの入院 | 240円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 190円 | |
| 低所得者1 |
110円 |
|
所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります
特定疾病療養受療証について
以下の対象疾病に該当する人は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を発行することができます。この証を医療機関に提示すると、自己負担限度額で対象疾病の治療を受けることができます。
対象疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る)
(厚生労働大臣の定める者とは、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている人)
自己負担限度額・証有効期限
| 上位所得者※1 | 上位所得者以外 | 有効期限 | |
| 70歳未満 | 20,000円 | 10,000円 | 毎年7月末 |
| 70歳以上 | 10,000円 | 10,000円 | なし |
※1 上位所得者とは、同一世帯の国保加入者の基礎控除後総所得金額の合計が600万円を超える世帯の人
【申請に必要なもの】
・国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(医師の意見書欄に記入があるもの)
・マイナンバーカード又は、資格確認書
※世帯主が申請者になります。申請者が世帯主以外の場合、委任状(20KB)(Word文書)が必要になります。
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
出産育児一時金について
妊娠12週(85日)以降で出産したときは(流産・死産も対象となります)、申請により出産育児一時金が支給されます。
ただし、会社等を退職してから6か月以内の出産の場合は、加入していた健康保険から支給される場合があります。他の健康保険から支給があった場合は、国保からの支給はありません。
支給額
〇産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降の出産の場合
出生児1人につき500,000円(※双子の出産の場合は、500,000円×2=1,000,000円が出産育児一時金の額になります)
〇産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合や妊娠22週未満の産科医療補償制度加算対象外の出産の場合
出生児1人につき488,000円
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営している制度です。
出産育児一時金直接支払制度
出産育児一時金の範囲内において、出産にかかる費用を国保から医療機関等に直接支払うことにより、国保加入者の負担を少なくすることができる制度です。
出産費用が出産育児一時金を超える場合は、超過分のみを医療機関等に支払えばよく、高額な出産費用を立て替える必要がありません。
≪この直接支払制度を利用するためには、分娩を行う医療機関等と合意文書を取り交わす必要があります。詳しくは、出産予定の医療機関等へお問い合わせください。≫
また、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、医療機関等に支払った残額が世帯主に支給されますので、差額支給申請をしてください。
【申請に必要なもの】
・マイナンバーカード又は、資格確認書
・母子手帳
・医療機関等の領収書
・直接支払制度を利用した(または利用しない)旨の同意書
・振込口座のわかるもの(通帳など)
・分娩者及び世帯主の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
※世帯主が申請者になります。申請者が世帯主以外の場合、委任状(20KB)(Word文書)が必要になります。
・死産証明書又は死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠12週以降の死産、流産の場合のみ)
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
葬祭費について
国保に加入していた人が亡くなったとき、申請により葬儀を行った人(喪主)に葬祭費(30,000円)が支給されますので申請をしてください。
ただし、会社等を退職してから3か月以内に亡くなった場合は、加入していた健康保険から支給される場合があります。他の健康保険から支給があった場合は、国保からの支給はありません。
【申請に必要なもの】
・亡くなった人の資格確認書(保険証)
・振込口座のわかるもの(通帳など)
※喪主が申請者になります。申請者が喪主以外の場合、委任状(20KB)(Word文書)が必要になります。
・同一世帯の国保加入者の保険証(世帯主が亡くなった場合のみ)
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- このページに関するお問い合わせ先
- 隠岐の島町役場 町民課 国保年金係
電話番号:08512-2-8560
FAX番号:08512-2-4997
メールアドレス:choumin@town.okinoshima.shimane.jp
©
OKINOSHIMA Town. All Rights Reserved.